【感想】「教養としてのワイン」ワイン初心者にオススメの本
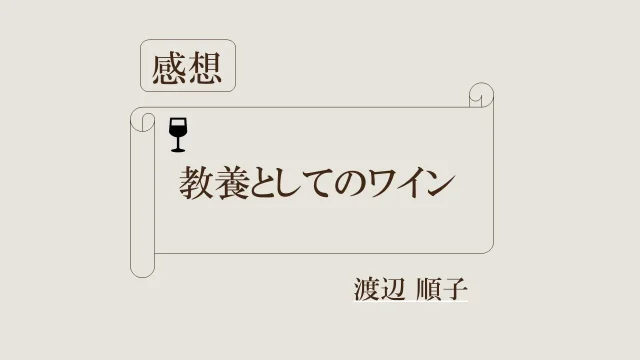
こんにちは。つぼたっくのあおいです。
ワインってなんとなくおしゃれですよね。
もともとお酒はそこまで好きではないのですが、社会人になったのをきっかけに少しだけワインの勉強をしてみたいと思いこの本を購入しました。
ワインの知識がほとんど無い自分が
「世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン」を読んだ感想や身についた知識などについて紹介します。
書籍紹介
基本情報
題名:世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン
著者:渡辺 順子
初版発行日:2018年9月19日
出版社:ダイヤモンド社
値段:1600円+税
概要
ワインは最強のビジネスツール
というのも、世界各国(特に欧米)では一流ビジネスパーソンがワインを学んでいます。
欧米では、無難な会話の1つとしてワインの話題を好み、お偉いさんほどワインが話題に上がるのだそうです。
ワインについて語り合うことで会食が盛り上がり、また交流が広がります。
このように世界で通用するワインの知識を初心者向けに解説してくれているのが、「教養としてのワイン」です。
この本を読むと、初歩的な知識、歴史やワインにまつわるエピソード、豆知識など教養として身につけるべきことを学ぶことができます。
例えば「ボジョレー解禁で盛り上がるのは日本だけ」
、「シャンパンはうっかりミスから生まれたもの」
のような他の人に話したくなるような知識がたくさん詰まっています。
また、本の所々で「初心者のためのワイン講義」として超基本的な知識が説明されており、ワインについての知識ゼロな人はそこだけ読んでも楽しめるのではないでしょうか。
感想
本当に初心者向け?
自分はワインの知識ゼロの初心者(もちろんビジネスエリートではなく、グローバルな仕事もしていない)ですが、
普通に楽しめました。
概要でも書きましたが、それぞれの国ごとの歴史やエピソードなどが詳しく説明されています。
そのため、最後まで飽きずに読み切ることができました。
ワインを趣味として楽しむなら、この本を読むだけで十分です。
この本を一回通り読むことで知識がつきますし、ワインを購入したり飲んだりすることが楽しくなります。
そして、ちょっとした雑学として使える知識はたくさん身につくと思います。
実家で父とワインを飲んだ時にこの本で学んだことを話すと、
「よく知っているなあ!」と感心され、ワインの話で盛り上がりました。
ビジネスではありませんが、家庭でのコミュニケーションを円滑にするツールとしてもワインは重宝しますね!
ただ、本当にビジネスの場で使おうと思うなら要注意です。
この本を何度も読み返し実際に様々なワインを飲む必要があるなと感じました。
1回軽く読んだだけでは知識は定着しません。
やはり実際にワインを飲んでみないと分からないことが多いです。
この本を入り口に、ワインに触れる機会が増やす。
そして、ワインについての知識や経験を付けていくというのが理想的ではないでしょうか。
フランスとイタリア
初心者の自分もワインと言えばこの2国だということは知っていました(笑)
でもフランスワインとイタリアワインの違いなんて考えたこともない…
両方ともワインが有名ということしか知らなかったです。
この本では1部でフランスについて、2部でイタリアについて紹介しています。
本の半分以上がこの2国のワインの紹介なんですね。
(2部の後半はドイツやスペイン、イギリスなどのヨーロッパワインも紹介されている)
それだけ、ワインを語る上でこの2国は重要ということなのです。
全部説明するときりがないので、イタリアとフランスについて自分なりに簡単にまとめてみました。
| フランス | イタリア | |
| 主な生産地区 | ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、ローヌなど | ピエモンテ、ヴェネト、トスカーナなど |
| 格付け方法や規制 | めっちゃ厳しい | 緩い感じ |
| 高級度合い | 高い | フランスには劣る |
| ターゲット層 | 王族向け | 庶民向け |
| 土着品種 ※その土地でしか栽培されないブドウ品種 | 約100種 | 約2000種 |
ざっくりまとめるとこんな感じです。(本には詳細に説明がされているので、どっちかというと…という観点でまとめています)
本書では歴史的背景や、国ごとの文化や国民性などの観点からもイタリアワインとフランスワインを比較しています。
へ~っとなることがたくさん書いてあるので是非読んでみて欲しいです!
様々なことがその土地のワインに反映されているのが分かります。
ワインって深いなあとしみじみと感じました。
日本ワインはどうなのよ
3部では主に新興国ワインやビジネスとしてのワインについて紹介がされています。
例えば、アメリカのカリフォルニアワインがフランスワインに勝利したことや、チリでは安くて美味しいワインが作られていることなどです。
また、投資対象として見たときのワインについてや、偽ワイン事件などについても取り上げています。
その中で、日本のワインについても少しだけ触れられています。
結論から言うと、日本ワインはまだまだこれから…だそうです。
確かに、日本ワインってあまり聞いたことがありませんでしたが、評価が低いのは少しショックです…
しかし、最近では2018年からはワインの品質とブランドを守る基準が適応されます。
現在はまだまだですが、筆者は以下のように言っています。
日本の得意なモノづくりの技術を駆使すれば、ますます日本ワインの品質は高まり、海外の銘醸ワインと同等の味わいをつくり出せるでしょう。
日本人として、自分も日本のワインを応援していきたいです!
この本はこんな人にオススメ
この本は以下のような人にとってオススメだと思います。
- ワインに少しでも興味がある人
- ワインの歴史や特色などの知識を学びたい人
- ビジネスパーソンとして、グローバルな仕事をしたい人
- ワインが好きな人
まとめ
- 初心者にも分かりやすい内容になっている
- ワインやワインの生産国の歴史や特色などの知識を学ぶことができる
- フランスとイタリアのワインは世界的に有名
- 最近はアメリカのワインが注目されている
- 日本ワインはまだまだこれから
今回は「世界のビジネスエリートが身につける 教養としてのワイン」について紹介しました。
自分自身ワインについて全く知らなかったので、この本のことすべてが新鮮でとても楽しみながら読むことができました。
この本を読み終わったら早速ワインが飲みたくなり、早速近くのお店まで買いに行きました。
コンビニで適当に選んだワインしか買ったことが無い自分からすると、
ワインの生産地や甘さ、使われているブドウの品種まで気にしてワインを選ぶことがとても楽しかったです。
まだまだビジネスエリートとは程遠いですが、教養としてワインの知識をたくさんつけていきたいなと思わせてくれる本でした。
最後まで読んでいただきありがとうございました。



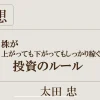
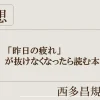
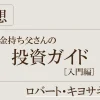
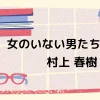
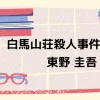
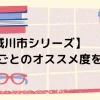
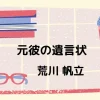
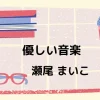
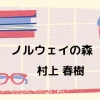
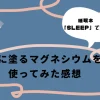
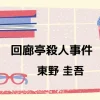
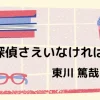
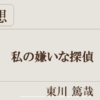
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません